声の素材が良い人ほど、「滑舌面で不利である」は本当か?
今日の2つ目の話題。今お風呂で思いついたので書きます。
これ、実は本当です。
声の素材が良いと、滑舌の良しあしのジャッジメントが一般的に厳しくなります。というよりも、正しくは「耳についてしまう」のです。
声の素材が良ければよいほど、「滑舌はこうあって欲しい」という所に耳が向いてしまうんですよね。
例えば、映画のセリフで、「貴様の心臓の音を、一分一秒でも早く止めてやろうか!」というセリフがあったとして、
「一分一秒でも」の所で、い、いちびょぃお なんて、ヨロヨロもつれてしまったら、せっかくの美声のダークボイスなのに、勿体なくないですか?期待していただけに「こけ!」っといってしまいます。
実は私の生徒さんの割合は、性別でいうと女性が6割男性4割の割合なのですが、滑舌の問題を多く抱えるのは、比較的男性に多い気がします・・・
気のせいなのかな?と思ってよくよく考えてみたのですが、うちに限ってはそうですね。
セリフやナレーションで人々が求める声の要素は、
音程(音感)・スピード感(テンポ)フレーズ感(読む際のフレーズのつかみ方)だと思っています。
特に、抑揚など、誰かの読みを完コピしたいときには、上記の3つの要素が抑えられていれば何の問題もなく、完コピできるはずです。
では、滑舌は、上記の3つの要素の中の一体どれと強くかかわりがあると思いますか?・・・
実は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全部です。
特に、滑舌と音程は=になる方は少ないと思いますが、音程と滑舌はかなり密接な関係にあります。特に母音の置き方ははっきりいってほぼ「音程」の要素と「強さ」の要素です。
滑舌を安易に子音だけのものとしてとらえる方が多いですが、実は滑舌の重要な要素を占める割合は、私個人的には母音が6割以上だと考えています。
次に、「スピード感」。これもイメージ出来ると思いますが、滑舌が悪かったら言葉が滑らかに滑りませんし、単語単位で滑らかにできなければ、フレーズもうまくつながりません。
そして、最後の「フレーズ感」ですが、これは音程、音感とかなり密接な関係にあります。テクニックとして、わざと声を裏声にひっくりかえらせて抑揚をつけた読みをしたり、語尾をきゅっとしゃくりあげて、独自のキャラクターを表現する方もいらっしゃいます。
特に変わった抑揚をつけたりするときは、その抑揚のお陰で滑舌がごまかせる場合も時にはありますが、大抵は声の上下を駆使したりするので、声帯の遣い方が「音程」に引っ張られたりすると、うまく言葉のデコレーションが出来なかったりします。
というように、人の真似をしてみるとよくわかるのですが、キャラクター性を出しつつも、滑舌よく喋るというのは、並大抵ではできません。
日ごろから、どんな読み方でも言葉がキレイに羅列されているように、訓練を積むことが大切だと感じています。

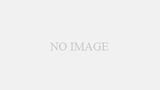
コメント